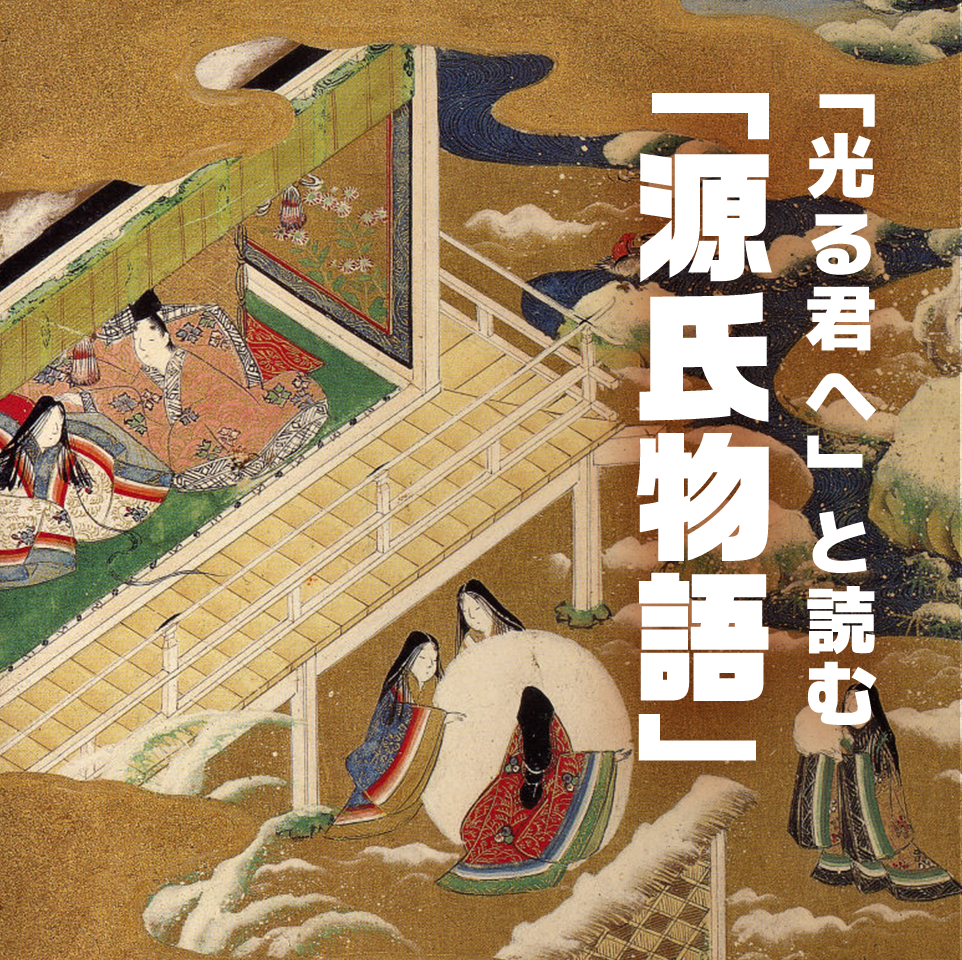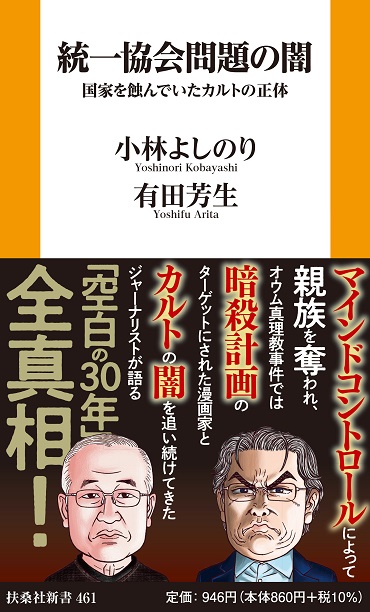國學院大學博物館の企画展「性別越境の歴史学」を観に行った。
平日の昼間なのに、老若男女が絶えず見学に訪れている。
女が男で、男が女でーーー。
こういう曖昧な性に興味を引かれる日本人は多いようだ。
解説パネルでは、性別の明確な区分けがなされたのは近代化のためだとはっきり書かれていた。
19世紀の欧米社会では「男/女」による異性愛を当然とし、異性装を禁忌とするキリスト教的倫理観が支配的であった。このような価値観を背景とする欧米と伍していくことが目指された近代日本では、幕末まで一般的に見られた異性装や同性愛の伝統が、恥ずべき陋習とされ、国家権力によって抑圧されるようになっていく。
一方、古代日本では、『古事記』や『日本書紀』などで、登場人物が異性装をすることで尋常でない力を発揮するエピソードがある。
アマテラスがミヅラを結ってスサノヲを待ち受けたり、カワカミノタケルの館に潜入したヤマトタケルが髪をほどいて少女の姿になったり。新羅征途のオキナガタラシヒメがやはりミヅラを結って男装したり・・・。
男でもあり、女でもある。
こうした双性的な存在は、常人とは異なる力の源泉となり、ある種の神性を帯びる。
企画展の監修者である三橋順子は、これを「双性原理」と呼んでいるという。
今だって、こうした日本人の感覚は受け継がれているのではないか?
歌舞伎の女形しかり、宝塚の男役しかり。
それを尊く美しいと感じる心は、私の中にもはっきりある。
映画『国宝』の吉沢亮には見とれたし、宝塚でトップスターだった人の
お芝居などは今でも憧れているから観に行ったりする。
人間が神に近づくなどとする発想は、確かに一神教ではタブー視されるだろう。
でも、日本ではもともとタブーどころか異能の発露であり、尊いものだったのだ。
その双性原理が、明治の近代化でことごとく抑圧された。
「男女七歳にして席を同じゅうせず」といった儒教的価値観も広まっていく。
旧制中学の「修身」では、とくに女性に対して「婦道」が説かれ、良妻賢母の涵養が良しとされた。
うわわ、私が卒業した大学のモットーは、そういえば「良妻賢母」だったことを思い出した。
家政学部がメインストリームだった(ちなみに私の選択は亜流の日本文学)。
どちらも入学してからわかったことだけど、あの頃、女に生まれたというだけで、良き妻であり賢い母であることが求められる世の縛りに反吐が出る思いだった。
ばけばけのヘブン先生じゃないけど、「ジゴク!!」と思っていた。さすがに今はそこまで大っぴらには良妻賢母を打ち出してはいないけど、建学の精神であったことは間違いない。
今の「男らしさ」とか「女らしさ」なんて、近代以降の所産に過ぎないということが、よくわかる企画展だった。
皇統の男系継承なんて、こうした文化的側面からもあり得ないということがはっきりわかる。西洋的な価値観&儒教にかぶれた明治絶対主義でしかない。